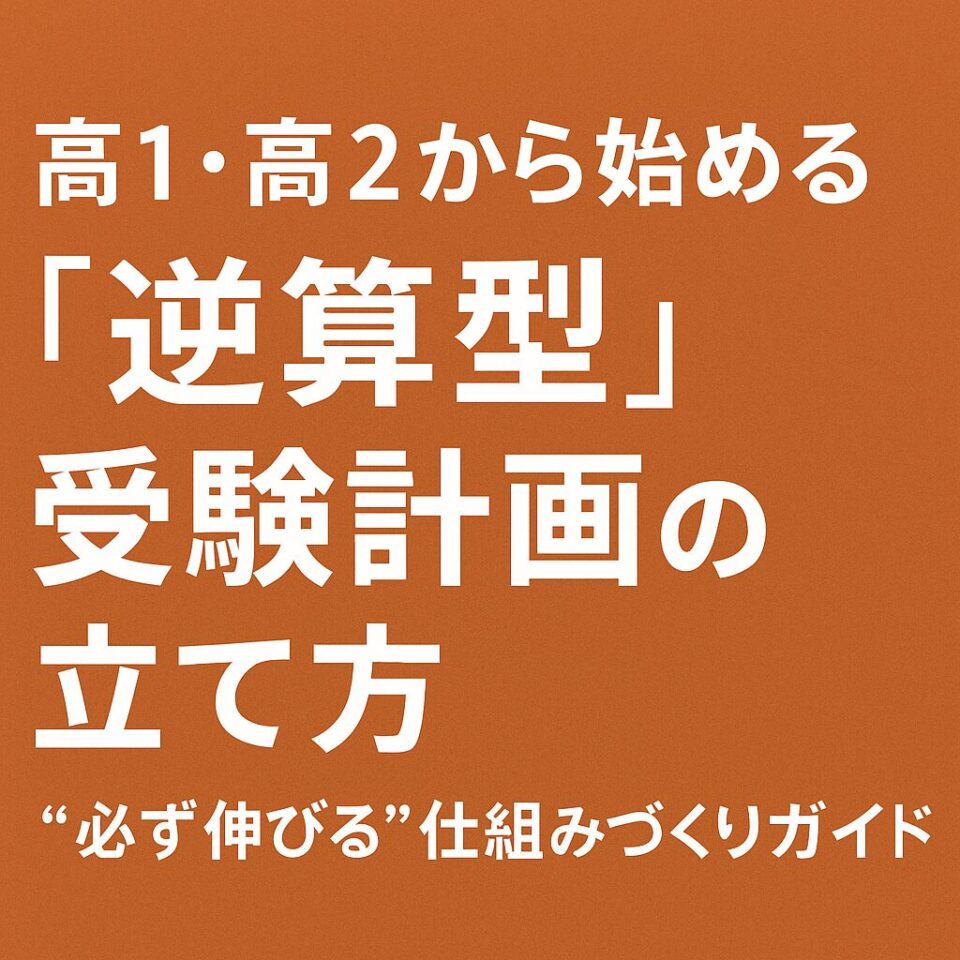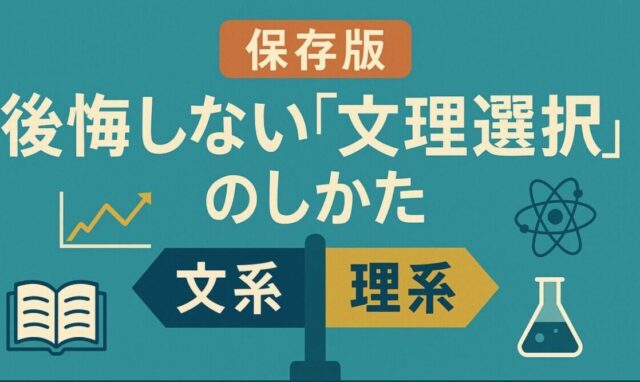はじめに:「とりあえず勉強」では、なかなか伸びない
- 高1・高2のうちから勉強しているのに、偏差値があまり変わらない
- テスト前だけ一気に詰め込んで、そのあと忘れてしまう
こうなる一番の原因は、ゴールから逆算されていない勉強だからです。
この記事では、
- 高1・高2からできる「逆算型」の受験計画の立て方
- 誰でも点数が“じわじわ必ず伸びる”勉強の仕組み
を、テンプレつきで解説します。
読みながらノートに写して、そのまま自分用の計画に変えてみてください。
逆算型勉強とは?ざっくりイメージ
逆算型 = 「ゴール → 中間目標 → 今日やること」
普通はこうなりがちです。
「今日は世界史をやろうかな」
「とりあえず単語帳を30個」
逆算型は、順番が逆です。
- ゴール:高3の夏の模試で〇〇大学にA判定
- 中間目標:
- 高2の3月までに英単語〇〇まで完了
- 数学は基礎問題精講レベルを1周+2周目復習
- 今日やること:
- 単語30個(1周目)+昨日分の復習
- 数学チャートの例題5問
「ゴールがあるから、今日やることが決まる」のが逆算型です。
ゴールの決め方:志望校が決まっていなくてもOK
① 志望校が決まっている人
- 第一志望の大学・学部を書く
- 過去問や入試情報から、
- 必要な教科
- 共通テストの目標得点率
- 二次・個別試験の科目
をざっくりメモする
- そのうえで、「高3の夏模試でどれくらい取っていたいか」を決める
例)
- 共通テスト本番目標:8割
- 高3夏模試目標:7割
- 高2冬の目標:6割 という感じ。
② 志望校がまだぼんやりの人
この場合は、レベル帯でゴールを仮決めします。
- 「国公立か私立か」
- 「首都圏/地方」
- 「難易度:上位/中堅/それ以下」
くらいまで決めたら、そのレベルの大学の**共通テストボーダー(目安得点率)**をネットや資料で調べ、
「このへんを狙うなら、高3夏までに共通テスト6〜7割くらい取りたいな」とざっくり設定します。
※ここで決めたゴールは“仮”でOK。
高2・高3で志望が変わっても、そのとき修正すれば大丈夫です。
高1〜高2の「逆算ロードマップ」を作る
ゴールから3つのチェックポイントを作る
例:
高3夏の模試で共通テスト7割がゴールの場合
- CP1:高2の3月
- 英語:共通過去問で5.5〜6割
- 数学:教科書レベルと基礎問題精講レベルを1周
- 国語:現代文の基礎問題集1周、古典単語300語
- CP2:高2の夏
- 英語:単語帳1周+長文問題集の基礎レベル半分
- 数学:チャート例題レベルの8割を「見たことある」状態
- CP3:高1の終わり
- 英語:英文法の基礎を一通り学習
- 数学:I・Aの教科書例題+基本問題を一通り解ける
- 国語:現代文の読み方の参考書を1冊読む
このように、
ゴール(高3夏)
→ 高2末
→ 高2夏
→ 高1末
と、約半年〜1年ごとに「ここまでやる」ラインを決めておくと、逆算しやすくなります。
「必ず伸びる」4つの仕組み
計画だけ立てても、続かなければ意味がありません。
ここでは、**偏差値がじわじわ上がる人に共通する“仕組み”**を4つ紹介します。
仕組み① 『復習自動ルール』を決める
覚えたつもり → すぐ忘れるを防ぐために、
「いつ復習するか」をあらかじめルール化します。
おすすめは「1・3・7・14日復習法」。
- 新しく覚えたことは
- 1日後
- 3日後
- 7日後
- 14日後
に、さっと確認する
実践のコツ
ノートの上に日付スペースを作り、
4/1に学習したら、
4/2・4/4・4/8・4/15 に「✔」をつける欄を作る
→ 復習したらチェックを入れていく。
これだけで、忘れる前に思い出すサイクルができます。
仕組み② 「週テスト方式」でアウトプットを強制
インプットだけだと、「できる気がする」状態で止まりがちです。
そこで、毎週必ずアウトプットの時間を入れる仕組みを作ります。
やり方
- **毎週日曜(もしくは土曜)**に「自分模試」を実施
- 内容はその週にやった範囲だけでOK
- 英単語テスト:ランダムで30〜50問
- 数学:その週に解いた問題から5問
- 古典:単語テスト+文法1〜2問
テスト後は必ず、
- 何点だったか
- どの分野が弱かったか
- 来週は何を優先的にやるか
をノートに3行でメモ。
これを毎週繰り返すと、勝手にPDCAが回り始めます。
仕組み③ 「最低ライン学習時間」を決める
やる気に完全に頼ると、調子の悪い日には0分になってしまいます。
そこで、
「どんなに忙しくても、これだけは絶対にやる」
という**“底のライン”を決めてしまう**のが大事です。
例:高1・高2の最低ライン
- 平日:60分(30分×2でもOK)
- 休日:180分
内容は、
- 英単語
- 古文単語
- 数学の基礎問題
など「積み上げ型」の科目がおすすめです。
ポイントは、目標時間ではなく“最低”時間にすること。
調子がいい日はもっとやってOK、
しんどい日は「最低ラインだけ守る」。
こうすると、「勉強しない日」がゼロに近づきます。
仕組み④ 勉強の見える化(スタンプ&グラフ)
成果が見えると、人は続きやすいです。
逆に、見えないと
「こんなにやってるのに伸びない気がする」
と感じてしまいます。
具体的な方法
- カレンダーかノートに、
- 勉強したら「○」
- 最低ラインを超えたら「◎」
を書き込むスタンプ式にする
- 週末に「1週間の合計勉強時間」を計算し、
- バーグラフ(棒グラフ)のように書く
これを続けるだけで、
**「やってないから伸びてないのか」「やってるのにやり方が悪いのか」**がわかりやすくなり、修正がしやすくなります。
高1・高2のモデルスケジュール
平日(授業+部活あり)例
- 18:30 帰宅
- 19:00〜19:20 英単語(新出10+復習20)
- 19:20〜19:50 数学(その日の授業の復習+問題2〜3問)
- 20:00〜20:20 夕食
- 20:30〜21:00 学校課題
- 21:00〜21:20 古文単語・文法
→ 合計 約90分
「最低ライン60分」をクリアしつつ、
単語・数学・古文の“積み上げゾーン”を毎日回すイメージです。
休日(部活なし)例
- 午前:
- 9:00〜10:30 数学(問題演習)
- 10:40〜11:20 英語長文
- 午後:
- 14:00〜15:00 学校の復習・宿題
- 15:10〜15:40 英単語・古文単語
- 夜:
- 20:00〜20:30 一週間の振り返り&自分模試
→ 合計 約4時間
ここで**「週テスト」と「1週間の振り返り」をセットにする**のがポイントです。
よくある失敗パターンとその対策
失敗① 計画を細かくしすぎて3日で崩壊
- 「月曜:英語長文○ページ、数学チャート何問…」と
分単位でビッシリ決めると、1回崩れた時にやる気がなくなります。
対策
- 「毎日やる科目」と「週に3日でいい科目」に分ける
- 細かいページ数ではなく、**「この時間は数学ゾーン」**のように時間単位でざっくり決める
失敗② 苦手科目を後回しにし続ける
嫌いな科目ほど、テスト前に爆発します。
対策
- 苦手科目ほど、1回あたりの時間を短く・頻度を多く
- 例:英語が苦手 → 毎日15分×2回
- 「1問だけ」「5分だけ」から始める日があってもOK。
勉強ゼロの日を作らないことのほうが大事です。
失敗③ 模試を受けっぱなしで、解きっぱなし
模試後のノートが真っ白…は、かなりもったいないです。
対策:模試反省シート3行でOK
- できた分野
- できなかった分野
- 次の模試までにやること(具体的な参考書・単元)
これを1枚にまとめ、机の前に貼っておきます。
次の計画を立てるときは、まずここを見るようにすると、弱点が自然に計画に組み込まれます。
今日からできる行動チェックリスト
最後に、「読んで終わり」にしないための行動リストです。
この中から最低1つは、今日やってみてください。
- ゴール(高3夏の模試での目標)をノートの1ページ目に書く
- 高1末・高2夏・高2末の「中間目標」をざっくりでいいので決める
- 復習用に「1・3・7・14日チェック欄つきノート」のフォーマットを作る
- 来週の「自分模試」(範囲と時間)を決めて、カレンダーに書く
- 平日の最低ライン勉強時間(例:60分)を宣言する
- 今日から勉強した日は、カレンダーに○をつける「見える化」を始める
まとめ
- 高1・高2からの勉強は、逆算して「いつまでに何を終わらせるか」を決めることが大事
- 計画を“必ず伸びる仕組み”に変えるには、
- 復習の自動ルール
- 週テスト方式のアウトプット
- 最低ライン勉強時間
- 勉強の見える化
をセットにする
- 完璧な計画より、続く仕組みのほうが圧倒的に強い
「逆算型+仕組み化」ができれば、
高3になってから慌てることなく、じわじわ偏差値が上がっていくはずです。