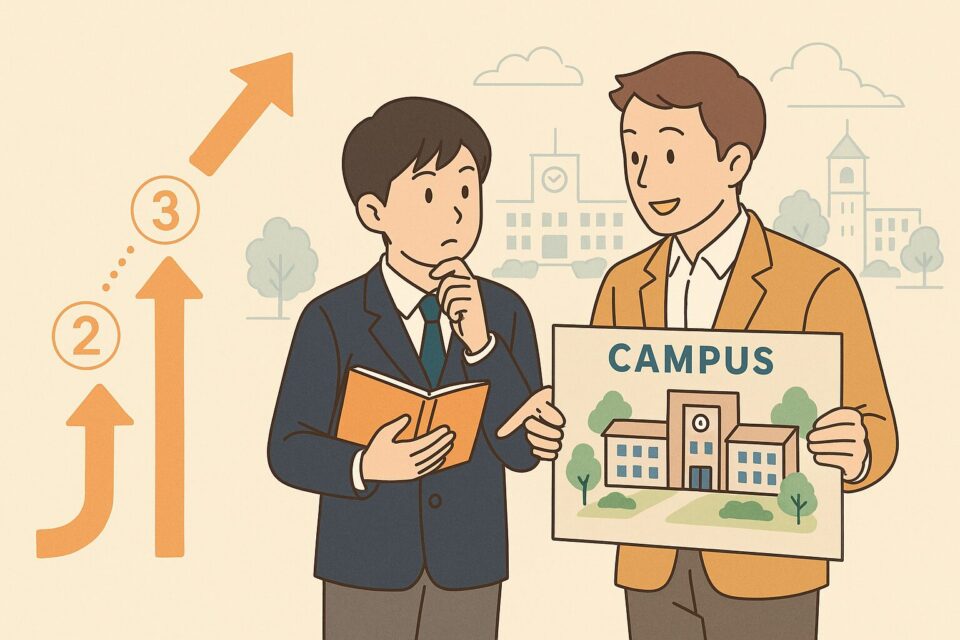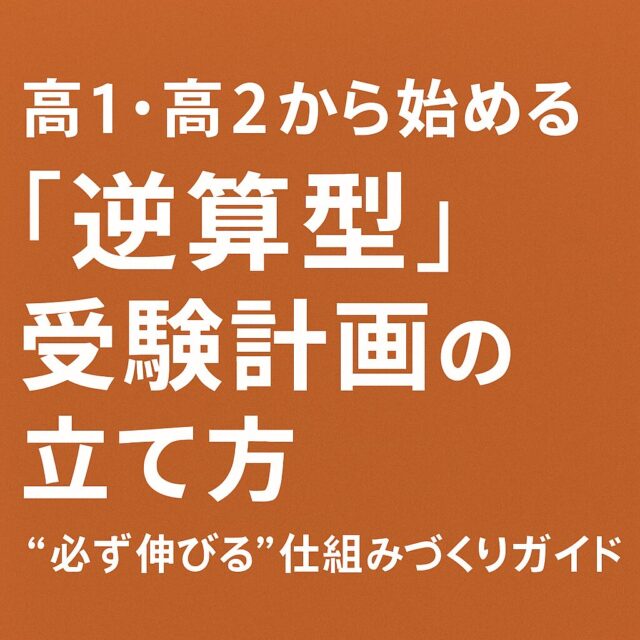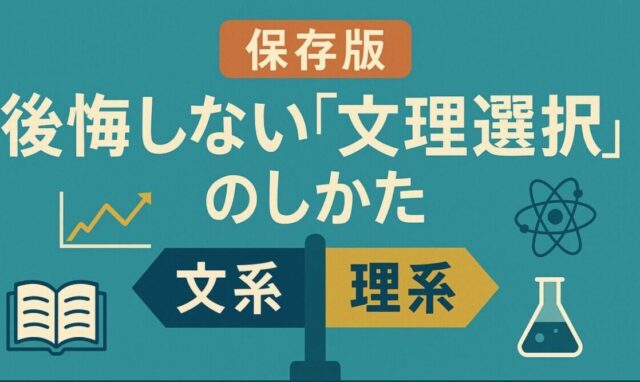はじめに
「志望校どうするの?」と先生や保護者に聞かれても、正直ピンとこない。
なんとなく行きたい学部はあるけれど、レベル感もよく分からないし、本当にそれでいいのか自信もない。
そんなモヤモヤを抱えたまま、気付けば高2・高3になって焦りだす生徒を、予備校でもたくさん見てきました。
実は、「志望校の決め方が分からない」という悩みは、とても自然なものです。情報も多すぎますし、「一度決めたら変えちゃいけない」と思い込んで、余計に動けなくなっている人も多いです。
この記事では、
「志望校の決め方が分からない状態」から抜け出すための3ステップ進路設計を、
高校生にも保護者にも分かりやすく解説します。
- なぜ志望校を早めに考えることが大事なのか
- よくある勘違いと、その落とし穴
- タイプ別に「今やるべきこと」が分かる行動例
- 今日から使えるチェックリスト
を用意しています。読み終わるころには、「とりあえずこれをやってみよう」と一歩踏み出せるはずです。一緒に整理していきましょう。
なぜこのテーマが大学受験で重要なのか
大学受験の勉強というと、多くの人が「とにかく偏差値を上げること」と考えがちです。
もちろん学力は大事ですが、「どこを目指すか」が決まっていないと、次のような問題が出てきます。
- どの科目をどのレベルまでやればいいか分からない
- 模試の判定を見ても、「良いのか悪いのか」判断できない
- 勉強の優先順位があいまいで、成績が伸びにくい
逆に、志望校(候補でもOK)がある程度決まっている生徒は、勉強の効率が一気に上がります。
- 必要な科目・配点が分かるので、時間のかけ方を調整できる
- 合格最低点やボーダーを知ることで、目標点がはっきりする
- 「この大学に行きたい」という気持ちが、最後の踏ん張りにつながる
つまり、志望校を決めることは、単なる「ゴールを決める作業」ではなく、
日々の勉強を意味のあるものに変えるスイッチでもあるのです。
よくある勘違い
志望校の決め方で、特に多い勘違いをいくつか挙げてみます。
- 「やりたいことが決まってないと志望校は決めちゃダメ」
→ 多くの高校生は、明確な「夢」なんて持っていません。興味のあることがぼんやりしていても、仮の方向性で動き始めて大丈夫です。 - 「一度決めた志望校は変えてはいけない」
→ むしろ、高2〜高3の間に“微調整”をするのは普通です。学力の伸びや新しい情報をもとに、柔軟に志望校を見直すのは戦略的な動きです。 - 「偏差値で決めればとりあえずOK」
→ 偏差値だけで決めると、入学後に「思っていたのと違う」とギャップを感じるリスクが高くなります。学びの内容やキャンパス環境も大事です。 - 「友達が行く大学に合わせれば安心」
→ 友達と一緒なのは心強いですが、将来やりたいことや得意科目は人それぞれ。自分に合わない選択をすると、途中でつらくなる可能性があります。
その勘違いが招くデメリット
上のような勘違いをそのままにしておくと、次のようなデメリットが出てきます。
- 動き出しが遅れる
「ちゃんと決まるまで待とう」と考えてしまい、高2終わり〜高3夏まで“情報ゼロ・行動ゼロ”の期間が続くことがあります。 - 勉強のやり直しが発生する
後から「やっぱり理系じゃなくて文系」「この大学は英語外部試験が必要だった」などが判明し、勉強のやり直し・科目変更で大きなロスになります。 - モチベーションが上がらない
目標がぼんやりしていると、「なんのために勉強しているのか」が分からなくなり、集中力が続きません。 - 合格しても満足できないリスク
偏差値やイメージだけで選んだ結果、「授業内容に興味が持てない」「キャンパスライフがしんどい」と感じて、せっかく合格した大学を楽しめないケースもあります。
だからこそ、「志望校の決め方」を早めに考えておくことが、
ムダな遠回りを減らし、勉強の効果を最大化するカギになるのです。
具体的な考え方・判断基準・勉強法
──3ステップ進路設計
ここからは、「志望校の決め方が分からない」を3ステップで整理する進路設計を紹介します。
- ステップ1:自分の「軸」をざっくり言葉にする
- ステップ2:大学・学部の情報を「比較」してみる
- ステップ3:仮の志望校から逆算して勉強計画を立てる
まず確認すべきポイント(ステップ1:自分の軸)
いきなり大学名から考えると、情報量が多すぎて混乱します。
まずは、次の5つのポイントについて、自分なりの「ざっくりした答え」を出してみましょう。完璧でなくてOKです。
- 文系か理系か
- 得意科目・苦手科目
- 好きな勉強のタイプ(計算・実験が好き/文章や社会問題を考えるのが好き など)
- 興味のあるテーマ・分野
- 人と関わる仕事に興味があるか
- データ・IT・ものづくりに興味があるか
- 経済・ビジネス・社会問題に興味があるか など
- 大学で重視したいこと
- 就職の強さ
- 留学・国際交流
- 研究環境・設備
- キャンパスの雰囲気(都会/自然/規模など)
- 通学エリア・一人暮らしの可否
- 自宅から通いたいか
- 一人暮らしも選択肢に入るか
- どうしても行きたい地方や都市はあるか
- 学力の現在地(模試偏差値の目安)
- 今の段階での模試結果
- 得意科目と伸びしろがありそうな科目
これらを紙やノートに箇条書きで書き出すだけでも、
「なんとなく」だった頭の中が、かなり整理されます。
タイプ別のおすすめ行動例(ステップ2:情報収集&比較)
次に、あなたのタイプ別に、「まずどんな行動から始めるといいか」を整理してみます。
① やりたいことはぼんやりあるタイプ
- 例:
「英語が好きで、将来は海外に関わる仕事がしたい」
「人の役に立つ仕事がしたいけど、具体的な職業はまだ決まっていない」
おすすめ行動
- 「◯◯学 どんなこと勉強」「◯◯系 学部一覧」で検索してみる
- 大学パンフレットやWebサイトで、学部の授業内容のページを読む
- オープンキャンパスやオンライン説明会で、学部紹介の動画を見る
- 英語が得意なら、英語を武器にできる学部(国際系・外国語・経済×グローバルなど)を複数ピックアップして比較する
② やりたいことが全く分からないタイプ
- 例:
「特に夢もなくて、興味もバラバラ」
「とりあえず大学には行きたいけど、何を基準に選べばいいか分からない」
おすすめ行動
- 文理どちらにするかを、科目の得意・不得意から考えてみる
- 「就職の幅が広い」「学べる分野が広め」の学部(経済・経営・総合政策・教養学部など)を候補に入れる
- 進路指導の先生や保護者に、「自分の長所・向いていそうな分野」を聞いてみる
- 高校や自治体が開催する進学ガイダンスで、複数学部の話を聞き比べる
③ 学びたいことははっきりしているが、大学レベルが分からないタイプ
- 例:
「心理学をやりたい」「建築を学びたい」が、どの大学を目指すべきか分からない
おすすめ行動
- 希望分野を扱う大学を、まずは偏差値に関係なくリストアップ
- その中から「上位〜中堅〜安全圏」の3グループに分けてみる
- 各大学の入試科目・配点・合格最低点を調べて、必要な学力レベルの目安を知る
- 模試の結果をもとに、「第一志望」「チャレンジ」「安全圏」の3種類の候補を作る
今日からできるチェックリスト(ステップ3:仮の志望校から逆算)
最後に、今日から実践できるチェックリストをまとめます。
全部を一気にやる必要はありません。まずはできそうなものから始めてみてください。
【ステップ1:自己整理】
- 文系・理系どちら寄りか、今の考えを書き出した
- 好きな科目・嫌いな科目を3つずつ書いてみた
- 興味があるキーワード(経済・心理・IT・教育など)を5つ書いた
- 通学エリア(一都三県、関西圏、地元など)の希望を書いた
【ステップ2:大学・学部の情報収集】
- 興味のある学部を3〜5個ピックアップした
- それぞれの大学の公式サイトで、学部紹介ページを読んだ
- オープンキャンパス・説明会の日程を1つ以上チェックした
- 模試の結果と照らし合わせて、「ちょうど良さそうなレベル」の大学を2〜3校メモした
【ステップ3:仮の志望校から勉強計画】
- 仮の第一志望(変わってOK)を紙に書いてみた
- その大学の入試科目・配点を調べた
- 必要な科目の中で、自分の弱点になりそうな科目を1つ選んだ
- その科目で「今週やること」を1つだけ決めた(例:英単語帳1日20語など)
このチェックリストを1つずつ埋めていくことで、「なんとなく不安…」が「やることは見えてきた」に変わっていきます。
実例・ケーススタディ
ここからは、予備校でよく見る「うまくいったパターン」と「つまずきやすいパターン」を、架空の例を通して紹介します。
ケース1:Aさん(高2・文系志望)/うまくいったパターン
- 状況:
高2の春。国語と英語は得意だが、将来の夢は特にない。なんとなく「文系かな」と思っているレベル。 - 行動:
- 先生に勧められて、まず「文系で学べる分野」を一覧でチェック
- 経済・心理・法学に少し興味を持ち、大学のパンフレットやWebでそれぞれの学部内容を調べる
- 高2の夏のオープンキャンパスで、経済学部と心理学部の模擬授業に参加
- 「数字が苦手だから心理かな」と思っていたが、経済の授業が意外と面白く、「経済×社会問題」に強く惹かれる
- 高2冬の段階で、「首都圏の経済学部」を中心に、第一志望〜安全圏まで5校をピックアップ
- 各大学の入試科目と配点を調べ、英語と数学を重点科目に設定して勉強をスタート
- 結果:
高3の夏までに、必要科目の基礎固めが終わり、秋以降は過去問対策に時間を回せた。
最終的に第一志望の経済学部に合格。入学後も「経済で社会問題を考える」という学びが楽しく、充実した大学生活を送っている。
ポイント
早い時期に「分野」レベルで興味を広げ、オープンキャンパスでの“発見”から志望校を具体化したパターンです。
「やりたいことが最初からハッキリしていたわけではない」点が重要です。
ケース2:Bさん(高3・理系志望)/つまずきやすいパターン
- 状況:
数学と理科が得意で、高1から「なんとなく理系」と決めていた。
しかし、具体的な学部は決めないまま、高3の夏まで模試だけ受けている状態。 - 行動:
- 学部選びを後回しにして、「とりあえず偏差値の高い大学を目指そう」と考える
- 高3夏の模試結果で、偏差値的に「工学部なら手が届きそう」と言われ、とりあえず工学部志望に
- 志望校の入試科目をしっかり調べないまま、学校や塾のペースで勉強
- 出願直前になって、「第一志望の大学は理科2科目必須」「別の候補は英語外部試験が必要」など条件の違いに気づく
- 慌てて科目の勉強を増やした結果、どの科目も中途半端な仕上がりに
- 結果:
不完全な準備のまま入試本番を迎え、第一志望を含む複数学部で不合格。
最終的には合格した大学に進学したものの、「もっと早く志望校を絞っておけば…」と後悔が残った。
ポイント
学部・大学によって入試科目や配点が大きく違うのに、
「なんとなく」で後回しにしたことで、勉強の優先順位を誤ってしまった例です。
ケース3:Cさん(高1・保護者の期待が強い)/ズレが生まれかけていたパターン
- 状況:
高1で成績は良好。保護者は「できれば国公立に行ってほしい」と考えているが、Cさん本人はまだ大学イメージが薄い。 - 行動:
- 保護者は「国公立」「理系」「安定」を重視している
- Cさんは実は社会科や文章を書くのが好きで、数学はそこまで得意ではない
- 進路面談で、担任の先生が「ご家庭と本人の希望」を両方聞き、違いに気付く
- 高1のうちに、保護者同席の三者面談で、「本人の得意科目・興味」を整理
- 結果的に、「文系国公立」「私立文系」両方を視野に入れつつ、文系科目を伸ばす方針に変更
- 結果:
高2で文理選択をするとき、大きな迷いなく文系を選択。
国公立文系と私立文系の両方を候補にしつつ、早めに英語と国語の基礎を固めることができた。
ポイント
「保護者の期待」と「本人の得意・興味」にズレがあると、後から大きなストレスになります。
早めに対話をして、方向性を“共有すること”がとても重要です。
まとめパート(結論)
ここまで、「志望校の決め方がわからない人のための3ステップ進路設計」を見てきました。最後に、ポイントを整理します。
◆ 記事の要点(3〜5個)
- 志望校を決めることは、「勉強の効率」と「モチベーション」を高めるための重要なステップです。
- 「やりたいことが決まってから」ではなく、「仮の方向性」で動き始めることが大切です。
- 文理、興味のあるテーマ、通学エリア、学力の現在地など、自分の「軸」をまずざっくりと言葉にしてみましょう。
- タイプ別に、オープンキャンパス・情報収集・模試結果の活用など、具体的な行動に落とし込むことができます。
- 今日から使えるチェックリストを埋めていくことで、「なんとなく不安」から「やるべきことが見える」状態に変わります。
◆ まず一歩目としてやってほしいこと
1枚の紙かノートを用意して、
「文系/理系」「好きな科目」「興味のあるキーワード5つ」「通いたいエリア」
この4つだけで良いので、今日中に書き出してみてください。
それが、あなたの進路設計の“スタート地点”になります。
◆ 高校生へのメッセージ
志望校は、「一瞬で完璧に決めるもの」ではなく、
行動しながら少しずつピントを合わせていくものです。
今はぼんやりしていても大丈夫。この記事の3ステップを使って、一緒に少しずつ進めていきましょう。
◆ 保護者の方へのメッセージ
お子さんは「進路」という、初めての大きな選択の前で不安を感じています。
正解を押し付けるのではなく、
「何に興味がある?」「得意なことは何だと思う?」と問いかけ、一緒に整理してあげる姿勢が、何よりの支えになります。
ぜひこの記事をきっかけに、親子で進路について対話する時間を作ってみてください。